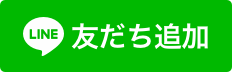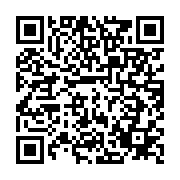自己破産後の生活はどうなる?クレジットカードへの影響は?
自己破産とは
破産とは、債務者が多額の借金などにより経済的に破綻してしまい、自分のもっている資産では全ての債権者に対して完全に弁済することができなくなった場合に、最低限の生活用品などを除いた全ての財産を換価して、全債権者にその債権額に応じて公平に弁済することを目的とする裁判上の手続きのことをいいます。
破産の申立ては債権者からもできますが、債務者自らが申し立てる破産を自己破産といいます。
自己破産をすると、周り近所にその事実が知られるのではないかと心配する方が多いのですが、そのような心配はまずないといっていいでしょう。
裁判所から破産手続開始決定を受けても戸籍や住民票に記載されることはないので、子供の就職や結婚などに影響が出ることはありません。
旧破産法の時代は、自己破産をした者は本籍地の市区町村役場の破産者名簿に記載されていました。
しかし、破産者名簿は非公開なので第三者が勝手に閲覧することはできませんし、免責決定を受けると破産者名簿からも抹消されます。
この点については、平成17年から施行された新破産法により、破産者名簿へ記載する規定が変わり、現在では破産手続き開始決定が出た後に免責許可が下りなかった場合にのみ破産者名簿に記載されるように取り扱いが変わっています。
一般の方はよく破産の申立てをすれば無条件で借金がなくなると思っています。
しかし、手続き上は破産手続き開始決定が出た後に、裁判所から免責決定を受けることで初めて借金がなくなるのです。
したがって、自己破産の最終的な目的は、免責決定を得ることであるといっても過言ではありません。
とはいえ、実務上は自己破産の申立をすると同時に免責の申立てもおこないます。
よって、破産手続き開始決定と免責決定を分けて考えることはありません。
実務上も破産手続開始決定が出て、免責決定が出ないということはほとんどありません。
自己破産の申立てから免責決定までは裁判所や個々の事情によっても多少の違いはありますが、およそ3か月から半年程度です。
当事務所の地元の千葉地方裁判所では、特に問題がなければ申し立てをしてから3か月程度で免責決定が出ていますが、この辺は各地の裁判所の運用や事案によって異なります。
これに対して、借入れ内容に問題があったり、破産者に一定程度の資産がある場合は管財事件になることがあります。
管財事件になった場合は申し立てをしてから免責決定までに半年から1年程度かかります。
当事務所に依頼をしてから申し立てをするまでに3か月~半年くらいかかることが多いです。
よって、依頼をしてから免責決定が出るまでのすべてを合わせた期間は半年~1年くらいとなります。
マイホームは手放すことになる
自己破産は借金整理の最終手段なので、必要最低限の生活用品を除く全ての財産は強制的に換価されて、債権者に平等に分配されます。
よって、マイホームを所有している場合は、原則的に裁判所による競売手続きによって自宅を手放すことになります。
しかし、自己破産を申し立てても、すぐに家を追い出されるというわけではなく、実際には新しい買主が現れるまでは従来どおりに住み続けることができます。
実務上は、自己破産の申立てをしてから不動産が売却されるまでに半年~1年程度かかることも珍しくなく、競売手続きの中で買い手が現れなければ追い出されることはありません。
自宅を任意売却して新たな所有者と新規に賃貸契約を締結することで、自宅の所有権は失いますがそのまま住み続けることができる場合があります(これをリースバックといいます)。
あわせて読みたい
自己破産は清算手続きなので、当然お金に換えることのできる物であれば強制処分されます。
ただし、債務者の最低限の生活は保証されているので、生活する上での必要最低限の家財道具は差押禁止財産として取上げられることはありません。
実務上は、およそ20万円以上の価値があるようなものでなければ配当に回ることはないので、よほど高価なものを持っていない限りは、自己破産をしても何も処分されないで済むケースが多いです。
よって、通常の生活で必要な家財道具や日用品が処分されることはまずありません。
官報への掲載と選挙権や資格制限
自己破産をした場合、裁判所から破産手続開始決定が出た時と免責許可決定をもらった時の合計2回は官報に掲載されます。
官報とは、政府が発行している新聞のようなものです。
しかし、一般人が官報などを見ることはまずありませんし、裁判所から勤務先の会社に連絡がいくようなこともありません。
よって、自己破産をしてもご近所や職場に知られる心配はほとんどありません。
また、自己破産をしても選挙権、被選挙権などの公民権は喪失しません。
しかし、破産者は司法書士、宅地建物取引士、生命保険募集人、警備員などの職に就くことはできなくなるなど一定の資格制限があります。
ただし、免責決定を受ければ、この資格制限もなくなります。
実務上、資格制限が問題になるのは相談者が警備員や保険外交員の仕事をしている場合です。
こういった場合は、自己破産ができないので任意整理や個人再生などを検討することになります。
ブラックリストへの登録
自己破産をすると、信用情報機関(JICC、CICなど)にいわゆるブラックとして登録されてしまいます。
この登録機関は、信用情報機関によって多少の違いがありますが、およそ5年~10年です。
このブラックリストに登録されると、その期間は銀行やサラ金からお金を借りたり、クレジット会社からカードの発行を受けることが困難となります。
しかし、日常生活で銀行や郵便局の口座を使ったり、公共料金の引き落としまでができなくなるわけではありません。
ブラックリストに登録されるのは自己破産に限った話ではなく、一定期間滞納した時点ですでに登録されているので、自己破産特有のデメリットとはいえません。
あわせて読みたい
自己破産のデメリットについて
自己破産は借金を帳消しにする究極の解決法ですが、一定のデメリットがあります。
以下では、自己破産をすることで日常生活にどのような影響があるのかを具体的に解説したいと思います。
主なデメリット
- 信用情報がいわゆるブラックになる
- マイホームを失う
- 一定の資格制限
- 官報に掲載される
- 連帯保証人が要る場合は保証人に請求がいく
- 転居の制限(管財事件の場合)
日常生活への影響
一般の方は、自己破産に対して非常に暗いイメージを持っているのが通常です。
自己破産をすると戸籍に記載されてしまうのではないか、公民権が剥奪されてしまうのではないか、子供の進学に悪影響が生じるのではないかなど、自己破産に対してマイナスのイメージを持っています。
しかし、自己破産をしても戸籍に記載されることはありませんし、選挙権も被選挙権もなくなりません。
もちろん、子供の進学に影響を与えることはありません。
旧破産法の時代は、破産手続開始決定が確定すると裁判所から破産者の本籍地の市区町村役場にその旨が通知されて破産者名簿に記載されていました。
しかし、平成17年の新破産法の施行により、免責決定が出た場合には破産者名簿へ掲載されない取り扱いになりました。
万が一、免責決定が出なかったとしても、社会生活の中で市区町村発行の身分証明書の提出を求められることは非常に少ないので、実際に問題になることはほとんどないといえます。
また、自己破産をしても会社を辞める必要はなく、これは公務員であっても同様です。
ただし、すでに裁判を起こされて判決などを取られていると、債権者から給与の差押えをされる可能性があり、その場合は勤務先に借金を滞納している事実が知られてしまいます。
そういった場合は、会社に居づらくなって退職せざるを得ない場合も中にはあります。
自己破産をすると債権者が自宅に押しかけてくるとか、家財道具にベタベタと差押えの赤紙が張られてしまうというイメージをお持ちの方も多いですが、実際にはそういうことはありません。
なぜなら、債権者は自己破産の申し立てによって取立行為が禁止されますし、債務者の生活に欠くことができない家財道具は法律により差押えが禁止されているからです。
では、自己破産による実際の不利益には何があるのでしょうか。
第一は、破産情報が信用情報機関に登録されることです。
一般的にブラックリストといわれているものです。
これにより、破産者本人は当然として、同居の家族がクレジットカードをつくることができず、クレジットを利用することができなくなります。
しかし、信用情報機関へは3ヶ月ほどの延滞でも登録されるので、長期に延滞している人は自己破産しなくてもすでに登録されている可能性が高いと思われます。
最近、問題になっているのが、ヤミ金業者から破産者へのダイレクトメールによる勧誘です。
これは、自己破産をすると破産者が官報に掲載されるからです。
一般人が官報を見ることはまずありませんが、ヤミ金業者はその情報を元に破産者へDMを送り、再び破産者を多重債務者に陥れようと勧誘してきます。
なぜならば、一度、自己破産をして免責を得ると、その後7年間は自己破産することができなくなるからです。
賃貸借契約への影響
アパート・マンションや借家などの賃借人が自己破産をした場合には、賃貸人から追い出されてしまうのではないかとの不安を抱いている方もいらっしゃると思います。
以前は、破産が賃貸借契約の解除事由になっていましたが、民法の改正によりこの規定は削除されました。
よって、現在では自己破産をしても家賃を滞納していない限り、退去させられることはありません。
資格制限
自己破産をするとさまざまな資格制限があります。
たとえば、弁護士・司法書士・税理士などの資格を失うことになったり、会社の役員の資格を失うなどです。
保険の外交員や証券外交員など、他人の財産を預かり、または管理する業務を一定の資格の下に行っている場合には、自己破産によってその業務を禁止される場合があります。
ただし、資格制限は免責決定と同時に復権するので、自己破産をしたからといって永久に資格制限がされるわけではありません。
転居等の制限
破産者に一定の財産があるなどして破産管財人が選任された場合は、破産者は裁判所の許可を得なければ転居や旅行をすることができません。
これは、破産者の逃走や財産隠匿行為を防止するためです。
実際には、一時的な外出ではなく相当期間にわたり居住場所を離れる場合に許可が必要となります。
しかし、実務的には、合理的な理由があれば問題なく許可が出されるので、債務者にとっては特に不利益になることはないといえます。
また、管財事件では、郵便物が破産管財人に配達されることになります。
これは、債権債務の調査のためなので、破産財団に関係ないものについては破産管財人から受け取ることができます。
これらの制限はあくまでも管財事件の場合であって、自己破産の9割を占める同時廃止事件の場合は転居等の制限はありません。
住宅の取扱い
自己破産を考えている方の中には『マイホームだけは手放したくない』と思っている方が非常に多いです。
自己破産をするとマイホームは処分されるので、どうしてもマイホームを手放さずに債務整理を行いたいと考えている方は個人再生の利用を検討する必要があります。
もっとも、自己破産を申し立てからといって、直ちに引越しをしなければならないというわけではありません。
なぜなら、破産管財人が住宅を処分するまでの数ヶ月間は従来どおり住み続けることができるからです。
また、住宅に抵当権などの担保が登記されている場合で、担保額が住宅の時価をはるかに上回るとき(1・5倍程度という取扱いが多い)には、他に価値のある財産がなければ破産管財人が選任されることはなく、同時廃止事件として処理されることが多いです。
ただし、時価の認定方法(固定資産税評価証明書、地元の不動産業者の査定書など)、被担保債権がどのくらい時価を上回っていれば同時廃止が認められるかなどの運用は、各地の裁判所によって異なります。
この場合、債務者が債権者の協力を得て任意売却するか、債権者の競売申立てにより住宅が他の第三者の手に渡るまでは、債務者が住宅に居住することが可能です。
その間は住宅ローンの支払いをせず、引越しを行うための金銭的な準備もある程度おこなうことができます。
保証人への影響
自己破産の申し立てをして破産手続開始決定・免責決定を受けても、保証人には何の影響も及ぼしません。
したがって、保証人は債権者から保証債務についての追求を受けることになります。
しかも、保証契約では債務者の破産申し立てが期限の利益喪失事由(分割払いができなくなる)とされていることが多いので、主債務者の自己破産の影響で、保証人も今後の対応を検討する必要があります。
保証人が支払不能であったり、収入が乏しく支払いが困難な状況にあれば、保証人も自己破産が必要な場合があります。
しかし、債権者は必ずしも保証人に対して一括請求を迫るわけではありません。
特にクレジット会社に見られる傾向ですが、従来どおりの割賦弁済金を保証人から支払うことを条件として一括請求をしないことも少なくありません。
自己破産の申し立てにかかる費用
自分でする場合(同時廃止事件の場合)
約1万5000円
(内訳:予納金 ➡ 約1万円、収入印紙 ➡ 1500円、郵便切手 ➡ 数千円)
※切手代は裁判所によって異なります
司法書士に依頼した場合
約1万5000円の実費 + 司法書士報酬(10~30万円)
※司法書士の報酬は事務所によって異なります
法テラスを利用した場合
法テラスは、国民の権利の平等な実現をはかるために、法律の専門家(弁護士・司法書士)による援助や、裁判のための費用を援助する制度です。
当事者の間の経済力の差が権利の差にならないように、社会的公平を確保するのが法テラスの目的で、利用するには一定の収入条件があります。
実際に法テラスを利用して自己破産の申し立てを司法書士に依頼した場合の料金は約10万円です。
当事務所は、法テラスに登録しているので、当事務所経由で法テラスへのお申し込みが可能です。
※利用者は毎月5000円を法テラスに分割で返済します
司法書士による自己破産手続き
自己破産の申し立てを自分でおこなうこともできます。
では、なぜ安くはない報酬を払ってまで司法書士に依頼をするのでしょうか?
自己破産は申し立てをすれば、すべてが終わるというものではありません。
申し立ても裁判所に受理されなければいけませんし、受理されたあとも免責決定を受けることができなければ借金はなくなりません。
司法書士に依頼すれば煩雑な書類の作成も全て代わりにしてくれて、書類も依頼者に最も適したものを作成してくれます。
なにより、確実に免責が受けられるようにバックアップしてくれます。
また、依頼者が一番不安に感じている債権者からの過酷な取立ても、司法書士に依頼をすればすぐに止めてもらうことができます。
報酬も分割払いに応じている事務所がほとんどですし、法テラスを利用すればそれほどの負担になることはありません。
よって、自己破産は司法書士に依頼されることをオススメします。
ただし、司法書士に依頼をして債権者からの請求が止まったことで安心してしまい、その後の必要書類の収集に協力してくれない依頼者の方がいます。
自分一人で手続するのに比べれば、司法書士に依頼をした方が圧倒的に負担は軽減されますが、裁判所に提出する書類の収集などは司法書士と協力して進めていく必要があります。
つまり、司法書士に依頼をしたからといっても、裁判所に申し立てをするには依頼者の方の協力が必要で、こちらが収集をお願いした書類を集めて頂けないと手続きを進めることができないわけです。
自己破産のご依頼をお受けしてよくあるのが、いくらお願いをしても書類を集めて頂けず、最終的には連絡も取れなくなり辞任に至るというパターンです。
こういった場合はいくら手続きを進めたくてもどうすることもできないので、司法書士に依頼をしたからといって安心せず、裁判所から免責決定を受けるその日までは気を抜いてはいけません。
よって、依頼をすればあとはすべて任せて何もしなくてよいというわけではありません。
司法書士に依頼するメリット
- 面倒な書類の作成をすべてやってもらえる
- 債権者からの取り立てがなくなる
- 免責を受けられる確率が高い
- 何よりも安心を手に入れることができる
司法書士に依頼するデメリット
- 報酬を支払わなければならない
自分で自己破産の申し立てをする場合
司法書士や弁護士に依頼をせずに自分で自己破産の申し立てをした場合は、実際に裁判所に申し立てをして受理されるまでは債権者からの書面や電話による請求が止まることはありません。
この点、司法書士などに依頼をした場合と比べると雲泥の差があります。
そもそも、返済することができなくなった債務者の方にとって、まず一番重要なことは日々の請求から解放されて平穏な日常を取り戻すことです。
この点、司法書士などに依頼をすればすぐに債権者に対して受任通知を送って請求が止まります。
これに対して、自分で申し立てをする場合は実際に裁判所に申し立てをして受付が受理されて、その受理票を債権者に郵送するまでは請求が止まることはありません。
一般的に自己破産の申立書類を準備するのに最低でも1~2か月はかかるので、その間の請求が止まるかどうかは債務者の方にとって非常に重要なポイントとなります。
実際に自己破産の申し立てを司法書士などに依頼をしないで自分でおこなう方は現在においてはほとんどいないと思われますが、ご相談に来られる多くの方が1日でも早く請求から解放されたいと思って、そのまま依頼をしているのが現実です。
請求が止まらないと精神的にも非常に不安定な状況が続き、自己破産の準備にも多大な悪影響があるので、よほどのことがない限りは司法書士などの専門家にお願いすることをおすすめします。
よくある質問
自己破産ってどういう制度なの?
自己破産は最後の手段
破産とは、債務者が多額の借金などにより経済的に破綻してしまい、自分のもっている資産では全ての債権者に対して完全に弁済することができなくなった場合に、最低限の生活用品などを除いた全ての財産を換価して、全債権者にその債権額に応じて公平に弁済することを目的とする裁判上の手続きのことをいいます。
破産の申立ては債権者からもできますが、債務者自らが申し立てる場合を自己破産といいます。
このように自己破産は必要最低限の財産以外は全て処分されてしまいますが、借金も全てなくなりますので債務整理の最後の手段といえるでしょう。
よく夜逃げや蒸発をする方がいますが、それでは何の解決にもなりません。
自己破産をすることで解決するのであれば、迷わず自己破産することをオススメします。
どのくらいの借金があれば自己破産ができるの?
支払不能とは
自己破産の申立てをするには破産原因が必要です。
この破産原因とは、つまり支払不能状態にあるということです。
したがって、自己破産の申し立てをして、裁判所に『申立人は支払不能の状態である』と認められることによって破産手続開始決定の決定がされることになります。
そして、この支払不能とは『債務者が弁済能力の欠乏のために即時に弁済すべき債務を一般的かつ継続的に弁済することができない客観的状態』をいうとされ以下の3つの要件が必要です。
要件 内容 弁済能力の欠乏 金銭や小切手のみならず信用・労務・技能によっても金銭を調達することができないことをいいます。
よって、財産がなくても債務者の信用や労力によって金銭を調達し得れば、弁済能力の欠乏とは言えず、財産はあってもそれを金銭に換えることが困難であれば弁済能力の欠乏といえます。履行にある債務の弁済不能 将来の債務や支払に猶予い期限が付けられている債務については、その期限到来前に支払不能になるということはありません。
よって、現時点で支払う必要のある債務に関して支払うことができない状態にある必要があります。支払不能が継続的・客観的である 支払い不能状態は継続的でなければいけませんので、一時的なお金の欠乏では支払い不能状態とはいえません。 支払い不能かどうかの判定は、その人の収入・資産状態・社会的地位によって大きく異なるので一概には言えません。
例えば、手取り月収が25万円前後のサラリーマンの場合、クレジットやサラ金からの借金の総額が300万円~400万円であれば、月々の支払が8万円~10万円になるので、配偶者や子どもの有無などの家族構成によっては支払い不能状態といえるでしょう。
支払い不能状態といえるかどうかの判定は難しい場合があるので、ご自分で決めつけずにまずはご相談ください。
自己破産をしたことは周りに知られてしまうの?
周りに知られることはほとんどない
自己破産をすると周り近所にその事実が知られるのではないかと心配する方が多いのですが、そのような心配はまずないといっていいでしょう。
破産手続開始決定を受けたからといって戸籍や住民票に記載されることはないので、子どもの就職や結婚などに影響が出ることはありません。
本籍地の市区町村役場の破産者名簿に記載されるかどうかですが、免責決定が出た場合は記載されることはありません。
免責決定が得られなかった場合でも、破産者名簿は第三者が勝手に見ることはできません。
破産手続開始決定と免責決定が出た際は官報に掲載されます。
しかし、一般人が官報などを見ることはまずないですし、裁判所から勤務先の会社に連絡がいくようなこともないので、会社をクビになるようなことはありません。
もし、会社に知れたとしても、破産したことをもってクビにすることは許されません。
しかし、現実には勤務先にサラ金業者から執拗な督促の電話がかかってくることもあり、これにより会社に知られてしまい居づらくなることは考えられます。
司法書士に自己破産の手続きを依頼した場合、すぐに債権者の請求を止めてもらえるので、会社に知られる心配はまずありません。
ただし、すでに判決などを取られている債権者がいる場合、裁判所への自己破産の申し立てが遅れると、給与の差し押さえを受けてしまうことがあり、それが原因で借金をしていることを会社に知られる場合があります。
自己破産をするとブラックリストに載ってしまうの?
ブラックリストに登録される
自己破産をすると、JICC、CICなどの信用情報機関に事故情報が掲載されてしまいます。
これがいわゆるブラックリストと呼ばれているものです。
事故情報が登録されている期間は、信用情報機関によって多少の違いがありますが、およそ5年~10年です。
あわせて読みたい
ブラックリストに登録されると、その期間は銀行やサラ金からお金を借りたり、クレジット会社からクレジットカードの発行を受けることが困難となります。
しかし、中には自己破産をすれば他の業者からの請求が止まり、返済に回せるお金ができることを逆手に取って、新たに融資をする悪質業者がいるので注意が必要です。
自己破産に回数制限はありませんが、少なくとも前回の免責決定から7年が経過していないと再度の自己破産はできないので、くれぐれも一度自己破産をしたならば同じ過ちを繰り返さないようにしてください。
自己破産をするとマイホームはどうなってしまうの?
マイホームは任意売却するか競売になる
自己破産は借金整理の最終手段なので、必要最低限の生活用品を除く全ての財産は強制的に換価されて、債権者に平等に分配されます(実務上は20万円以上の価値がある物が処分の対象となります)。
よって、マイホームのように非常に財産価値が高いものは、当然に換価されることになります。
実際には自己破産の申し立てをする前に任意売却をするか、裁判所による競売のどちらかです。
あわせて読みたい
裁判所による競売といっても、すぐに家を追い出されるというわけではありません。
新しい買主が現れるまでは従来どおりに住み続けることができます。
自己破産を申し立ててから不動産が売却されるまでに半年から1年近くかかることも珍しくないので、その間であれば追い出されることはないといえます。
自己破産をすると家財道具も差押えをされてしまうの?
よほど高価な物でない限り取り上げられることはない
自己破産は清算手続きなので、当然お金に換えることのできる物であれば強制処分されてしまいます。
しかし、債務者の最低限の生活は保証されています。
生活する上での必要最低限の家財道具は差し押さえ禁止財産とされているので取上げられることはありません。
実務上は、申し立てをした時点でおよそ20万円以上の価値がある物でなければ処分の対象となりません。
よって、家財道具が処分の対象になることはほとんどありません。
今住んでいるアパートを出なくてはいけないの?
アパートを追い出されることはまずない
自己破産をしたからといって、家賃をきちんと支払っている限りはアパートを追い出されてしまうことはありません。
自己破産したことを貸主(大家)に知られることも基本的にありません。
旧民法では『借家人が破産した場合には、家主は解約を申出ることができる』とされていましたが、改正によりこの規定は削除されました。
もちろん、既に家賃が何ヶ月も滞納されていれば、債務不履行による賃貸借契約の解除の可能性があるのは当然ですが、これは自己破産とは別の話です。
自己破産をすると保証人に迷惑はかかるの?
保証人には正直に事情を話しましょう
債務者本人が自己破産をして免責されたとしても、保証人の支払い義務までなくなるわけではありません。
よって、連帯保証人がいる場合は、そちらに借金の督促が集中することになります。
保証人に迷惑はかけられないといって自己破産を躊躇しても何の解決にもならないので、自己破産をする前に保証人にも今の実情を正直に話すべきです。
場合によっては保証人も自己破産をする必要がでてきますが、とにかく大切なことは保証人に対して誠意をもって全てをきちんと説明するということであり、そのような義務が債務者にはあります。
自己破産をすると銀行取引はできなくなるの?
通常の預金や公共料金の支払は問題ない
自己破産をすると当然ブラックリストに登録されてしまいますので、銀行から融資を受けることはできなくなります。
だからと言って、銀行や郵便局に預金をしたり公共料金の引き落としまでができなくなるわけではありません。
気をつけて欲しいのが、給与の振込先の金融機関に対して借金があるような場合や公共料金の支払いをクレジット会社のカードで支払っている場合です。
このような場合、その口座に給与が振込まれますと、その金融機関は自分の債権と給与を相殺したり、支払方法を変更しないといつまでたってもカードの売り上げが止まりません。
自己破産は、全ての債権者に対して平等に財産を分配する制度なので、このようなことがあると一部の債権者に対する弁済(これを「偏頗(へんぱ)弁済」といいます)とみなされる可能性があります。
偏頗弁済があると、そのあとの自己破産手続きに悪影響が出る可能性があるので、事前に給与の振込先口座を変更したり、カード払いにしている公共料金の支払い方法を変更する必要があります。
自己破産すると退職金や生命保険はどうなるの?
退職金や生命保険に影響が出る場合がある
退職金に関しては、現時点で辞めたと仮定した場合に支給される退職金の8分の1の金額を債権者の配当にまわすように指示されます(裁判所によって多少の違いがあります)。
もちろん、実際に会社を辞める必要はありませんが、裁判所から指示されたお金をすぐに用意することは困難なので、実務上は裁判所に一定の猶予期間をもらってその間に用意することが多いです。
生命保険は掛け捨てタイプのものであれば、そのまま継続できることがほとんどです。
これに対して、積み立てタイプの場合は解約の対象になることがあります。
解約になるかどうかの目安は、現時点での解約返戻金がおよそ20万円以上かどうかです。
20万円以上の解約金が発生する場合は財産とみなされ、債権者への分配対象となるのが原則です。
よって、申し立ての際に、積み立てタイプの生命保険がある場合は、保険会社から交付される解約返戻金の金額が分かる書類を添付する必要があります。
自己破産をすると選挙権や職業は制限を受けるの?
選挙権はあるが一定の資格や職種に制限がある
自己破産をしても選挙権や被選挙権などの公民権は喪失しません。
しかし、破産者には以下のような資格制限があります。
既に以下の資格や職種に就いていた人が破産をすれば、その資格や職を失うことになります。
ただし、免責決定を受ければ、この資格制限もなくなります。
資格制限の代表例
弁護士・公認会計士・司法書士・税理士・行政書士・宅地建物取引士・株式(有限)会社の取締役・警備員・生命保険の外交員など
自己破産すると業者からの取立てが厳しくならないの?
申し立てをすると取り立ては止まる
自己破産の申し立てをすると、裁判所から債権者へ意見聴取書が送付されますので、これにより債権者も債務者が破産の申し立てをしたことがわかります。
しかし、申し立てから意見聴取書が債権者に送付されるまでには若干時間があるので、自己破産の申し立てと同時に、全債権者に理票を送付した方がいいでしょう。
この受理票を送付したにも関わらず厳しい取立てを受けるようでしたら、監督行政庁に苦情申立てをして行政指導を求める申し立てをすればいいでしょう。
これに対して、司法書士などの専門家に依頼をした場合は、その時点で債権者からの請求が止まります。
審尋の日に債権者が来て文句を言われたりしないの?
まず業者は出席しない
当事務所の地元の千葉地方裁判所では、自己破産の申し立てをした後に、破産審尋と免責審尋が同時におこなわれます(同時廃止事件の場合)。
同時廃止事件の場合、債権者がこの審尋期日に出席してくることはありません。
意見がある場合は書面で意見を述べる仕組みになっていますが、実務上は意見書を提出してくることはほとんどありません。
管財事件になった場合は債権者集会が開かれますが、その場合でも一般的なサラ金やカード会社などの貸金業者が出席してくることはまずありません。
自己破産をするにはいくらくらいの費用がかかるの?
最低でも2万円程度は必要
自己破産の申し立てに必要な費用は以下のとおりです。
種類 金額 収入印紙代 1500円 郵便切手 数千円 予納金 約1万円(同時廃止事件の場合) ただし、これは自己破産の申し立てを全て自分でした場合の費用で、同時廃止事件の場合です。
借入原因に問題があったり、債権者に配当するだけの財産を保有している場合は管財事件になることがあります。
その場合、管財費用として裁判所に20~50万円を納める必要があります。
よって、自己破産の場合は同時廃止事件か管財事件かで費用が大きく異なるので注意してください。
また、司法書士や弁護士に依頼すれば別途報酬を支払う必要があります。
司法書士報酬は20万~30万円、弁護士報酬は20~50万円が相場です。
収入が一定水準以下の場合は法テラスの立替制度があり、この場合の司法書士報酬は約10万円、弁護士報酬は約15万円です。
法テラスへの返済は月5000円~1万円です。
自己破産の同時廃止ってなに?
自己破産申し立ての90%程度が同時破産廃止になる
債務者の財産が少なくて破産手続きの費用すら用意できない場合、破産手続きを進める意味がないので、こういう場合は破産手続開始決定と同時に、破産管財人を選任することなく破産手続きを終結してしまいます。
これを同時破産廃止(同時廃止)といいます。
こうなると、破産者の財産は一切換価処分されることなく、その後新たに取得した財産については破産者自らが自由に処分しても構わないことになり、居住制限もなくなります。
しかし、同時廃止といっても、債務者が破産者になることに変わりはありませんので一定の資格制限(司法書士・弁護士・税理士・会社役員など)があります。
破産手続開始決定後に破産管財人が選任され、現実に破産手続きが開始されはしたが、換価できるような財産が少なくて破産手続き費用も出せないと認められるときには、破産管財人が申立てるか又は裁判所の職権で破産廃止決定がされて、破産手続きを中止します。
これを異時破産廃止(異時廃止)といいます。
自己破産の免責決定ってなに?
免責決定を受けなければ何の意味もない
一般の方はよく破産の申立てをして破産手続開始決定を受ければ、借金がなくなると思っていますが、実際には免責決定を受けることで初めて借金がなくなります。
したがって、自己破産をする最終的な目的はこの免責決定を得ることです。
この免責決定が確定すると『復権』といって、債務者は破産手続開始決定のない以前の状態に戻り、公私の資格制限も解かれて全く普通に生活することができるようになります。
免責されない場合はあるの?
不許可事由に該当しない限り免責される
免責の申立てがあると、裁判所は破産者を免責するかどうか審理します。
そして、以下の免責不許可事由に該当しない限り免責決定をしなければいけません。
1 破産財団(破産手続開始決定時に破産者が持っていた財産)を隠したり、壊したり、債権者に不利益に処分したとき 2 破産財団の負担を偽って増加させたとき(虚偽の抵当権をつけるなど) 3 商業帳簿を作る義務があるのに作らなかったり、不正確または不正の記載をしたり、あるいは帳簿を隠したり、破り捨てたりしたとき 4 浪費や賭博などの射倖行為で著しく財産を減少させたり又は過大な債務を負担したとき 5 破産手続開始決定を遅らせる目的で著しく不利益な条件で債務を負担したり、信用取引で商品を買い入れ著しく不利な条件でこれを処分したとき 6 破産原因があるのに、ある債権者に特別の利益を与える目的で担保を提供したり、弁済期前に弁済するなどしたとき 7 破産手続開始決定前1年内に破産原因の事実があるのにそれがないことを信じさせるため詐術を使って信用取引により財産を得たとき 8 虚偽の債権者名簿を裁判所に提出し、または裁判所に対し財産状態につき虚偽の陳述をしたとき 9 破産者が免責申立前7年以内に免責を得たことがあるとき 10 破産法に定める破産者の義務に違反したとき 上記のいずれにも該当しないのであれば免責されますが、実際にはギャンブルや浪費が原因で自己破産の申し立てをした場合でも、裁判所の裁量によって免責になることがほとんどです。
実際に当事務所が手掛けた自己破産においては、そのすべておいて免責が認められています。
よって、自分で免責は無理だと決めつけないで、まずは司法書士などの専門家にご相談ください。
自己破産は司法書士にお願いしたほうがいいの?
司法書士にお願いするほうがよい
一昔前であれば自分で自己破産の申し立てをする人も一定数いましたが、現在ではほとんどの方が司法書士などの専門家にお願いしています。
司法書士にお願いすると報酬の負担が発生しますが、ほとんどの事務所が分割払いに応じています。
また、法テラスを利用すれば約10万円で済みます。
よって、自己破産は自分でするよりも、専門家に依頼をした方がよいでしょう。
司法書士に依頼するメリット
- 面倒な書類の作成をすべてやってもらえる
- 債権者からの取り立てがなくなる
- 免責を受けられる確率が高い
- 何よりも安心を手に入れることができる
裁判所には何回行くの?
同時廃止事件であれば1回で済む
当事務所の地元の千葉地裁では、同時廃止事件であれば裁判所に行くのは原則的に1回だけです。
出頭した際は裁判官と直接面談し、破産申立書や陳述書に記載された内容、自己破産を申し立てるに至った事情、例えば負債状況や資産状況、支払能力などについて質問されます。
面接時間は5~10分程度です。
これに対し、管財事件の場合は、最低1回から場合によっては数回裁判所に行きますが、事案によって異なります。
全ての手続が完了するまでにどのくらいかかるの?
3か月から半年くらいで終わることが多い
裁判所に自己破産の申し立てをしてから免責決定が出るまでは、裁判所や個々の事情によっても多少の違いはありますが、およそ3か月から半年程度です。
司法書士に自己破産の依頼をした場合、裁判所に申し立てをするまでに3か月程度はかかります。
よって、司法書士に依頼をしてから免責決定が出るまでは、早くても半年程度です。
司法書士に依頼をした場合、その時点で債権者の直接請求が止まるので、免責決定が出るまでに半年程度かかるとはいっても、その間は債権者への返済をする必要はありません。
自己破産の申立てをするには何を用意するの?
必要書類は裁判所によって若干違う
裁判所に自己破産を申立てる場合に必要な書類を以下のとおりですが、申立書の書式や必要書類は全国の裁判所ごとに若干の違いがあります。
必要書類
- 住民票
- 戸籍謄本
- 給与明細(2~3か月分)
- 源泉徴収票(もしくは課税所得証明書)
- 預金通帳(1~2年分)
- 賃貸契約書の写し(賃貸の場合)
- 不動産の登記事項証明書(不動産を所有している場合)
- 退職金を証明する書面(現在の会社に5年以上勤めている場合)
- 車検証
- 保険証券解約返戻金の有無が分かる書類(積立型の保険を契約している場合)
債権者一覧表を作成する上で気をつけることは?
すべての借金を記載する
司法書士や弁護士に依頼をした場合は、債権者一覧表を自分で作成する必要はありません。
以下は、自分で自己破産の申し立てをする場合です。
債権者一覧表には、銀行等の一般の金融機関・家族・友人からの借入れ等をすべて漏れなく記入します。
他人の借入れについて保証人となっている場合はその保証債務も含まれます。
すでに時効期間が経過している債権者についても、消滅時効を援用して明確に紛争解決しているものを除き、後日の紛争を防止するために記載しましょう。
あわせて読みたい
すでに廃業した債権者もすべて記載します。
故意に一部の債権者を記入しないと免責不許可事由に該当するおそれがあるので注意してください。
債権者一覧表に記載した住所等が間違っていたり、移転等によって破産手続関係書類が債権者に届かなかった場合や、失念等により債権者一覧表に記載を漏らした債権者に対する破産の効果はどうなるのでしょうか?
これについては意見の対立があるものの原則的に破産の効果は及ぶと考えられています。
ただし、明確な根拠条文がないため、あとで争いになる可能性があります。
よって、必ず債権者一覧表には全ての債権者を記載するように心がけましょう。
ところで、債権者一覧表を作成しようにも、どこの業者からいくら借りていて、残債務が現在いくら残っているのかが把握できない場合があります。
契約書や利用明細書の控えが存在していればよいのですが、他人に知られたくないと思いそれらを全て処分してしまっているケースも少なくありません。
このような場合は信用情報機関(JICC、CICなど)を利用して自分の借入状況を調査することができます。
これらの信用情報機関には『いつ、どこから、いくら借りて、現在いくら残っているか』という情報が蓄積されています。
ですから、最寄りの窓口に開示請求をしてみるのがいいでしょう。
受付方法は原則的には来所ですが郵送による開示も可能です。 開示請求できるのは情報の開示を希望する本人で、請求に際しては本人であることを証明できる本人確認書類(免許証など)や印鑑が必要になります。
裁判所に申立て書類を提出する際の注意点
予納金を納付する必要がある
裁判所に自己破産を申請する場合は1万円程度の予納金が必要です。
この中には、破産手続開始決定と免責決定を官報(政府発行の機関紙)に掲載する費用が含まれます。
予納金は、申立ての際に受け取る納付書に必要事項を記入して裁判所の会計課にお金と一緒に持参すればすぐに終了します。
予納金は必ずしも申立てと同時に収める必要はありませんが、これを納付しないと自己破産の手続が先に進みません。
もし、長期納付しないでいると自己破産の申立て自体が却下されるので、できるだけ申立てと同時に納付しましょう。
自己破産の申立て自体を郵送でおこなうこともできるので、その場合の予納手続は後日行うことになります。
郵送で申立てをする際は、普通郵便ではなく必ず書留で送りましょう。
また、数千円程度の郵便切手を添付する必要があります。
これは、裁判所が申立人と債権者に書類を郵送する際に使用するためです。
そして、申立てに際して一番重要なことは受付票(受理証明書)を交付してもらうことです。
本来であれば債権者である貸金業者は破産の申立てがあったことを知った時点で取立てが規制されていますが、破産の申立ての事実を口頭で伝えても簡単には取立てを止めてはくれないのが現状です。
よって、司法書士などの専門家が関与していない場合は、自己破産の受付票(受理証明書)を裁判所から交付してもらい、すぐに全債権者に送付するようにしてください。
自己破産手続の大まかな流れは?
トータルで3~6ヶ月かかる
千葉地裁における自己破産(同時廃止事件)の大まかな手続の流れは以下のとおりです。
申し立てから免責の決定が出るまでは約3か月ですが、裁判所によって多少運用が異なります(同時廃止事件の場合)。
- 1.自己破産の申立て
- 申立人の住所地を管轄する地方裁判所に申立書を提出します
- 2.裁判官との面接
- 裁判官からこれまでの経緯などを聞かれます
- 3.破産手続開始決定
- めぼしい財産がなければ同時廃止の決定がされます
- 4.免責の決定
- 同時破産廃止決定から2ヵ月くらいで免責決定が出ます
- 5.免責確定
- 免責確定により借金が全てなくなります